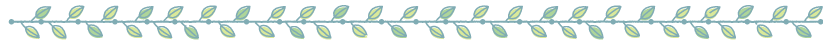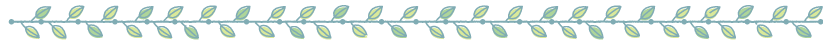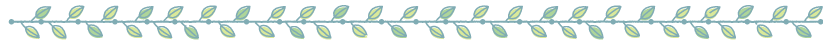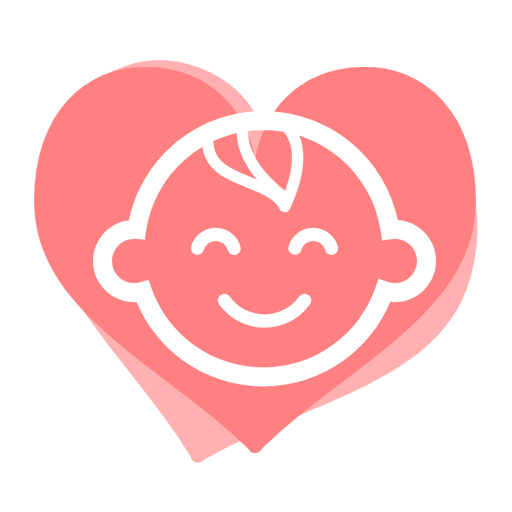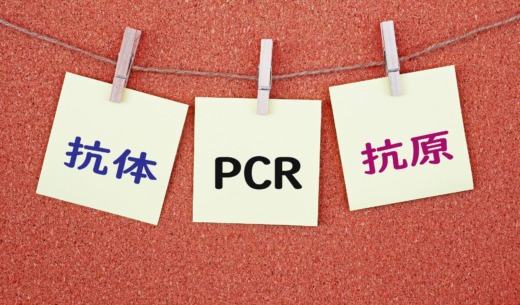冬物のコートを着ている人が日増しに増えてそろそろインフルエンザが心配になる季節になってきました。
今回は妊婦さんがインフルエンザにかかった時の対応方法やワクチンの摂取は安全か、そしてインフルエンザの予防方法を調べてみました。
インフルエンザ症状は?
日本におけるインフルエンザの診断と治療は、世界的に見ても進歩していると考えられています。
季節性インフルエンザは、主に冬期に流行するインフルエンザウイルスによる感染症で、急激な38度以上の発熱・頭痛・咳・咽頭痛・関節痛・筋肉痛などの症状が一般的です。
潜伏期間は1~5日(平均2日)で強い症状が続くのは3、4日~1週間ほどで治ります。乳幼児・高齢者・持病がある人は重症化しやすいとされ、妊婦さんもインフルエンザにかかると重症化しやすいとされています。
もしも妊婦さんがインフルエンザに感染したらどうすればいいの?
妊娠している方で、もしかしたらインフルエンザ?と疑われる場合には、かかりつけの産科を受診せず、内科の受診を推奨しています。
これは他の妊婦さんへの感染防止という観点からです。
自分が産婦人科に妊婦検診に行ったことがきっかけでインフルエンザにかかったら、、、嫌ですよね。
良識のある行動を妊婦さん同士が行うことでお互いにウィルス感染を防ぐことができます。
またインフルエンザウイルスによる赤ちゃんへの影響(奇形など)はあまりないといわれていますが、妊娠初期に適切な治療(発熱に対する解熱処置など)を行うことが大切ですよね。
今の医学ではインフルエンザウイルスと流産、早産の因果関係ははっきりしていません。
しかし、妊娠初期の高熱による流産の報告はあるのでインフルエンザにかかってしまったら重症化させないことが大切ですね。
腹痛、お腹のはり、性器出血、胎動がいつもより少ないなどの症状がないかを確認して、1つでも当てはまる場合は医師に相談するのがいいとされています。
日本では抗インフルエンザウイルス薬として「リレンザ」「タミフル」「イナビル」が使用できます。
これらインフルエンザウイルス薬は赤ちゃんへの悪影響は報告されていません。
また、家庭内で感染者がいる場合に予防的な投与も推奨されているので家族に感染者がでて心配な妊婦さんは医師に相談するのもいいですね。
妊娠中のインフルエンザワクチンは安全なの?
インフルエンザワクチンの母体および胎児への危険性は妊娠全期間を通じて極めて低いため、接種を希望される妊婦さんはワクチンを接種することができます。
インフルエンザワクチンはウイルスの病原性をなくした不活化ワクチンであり、妊婦さんや赤ちゃんへの悪影響はないと考えられています。
ワクチンの添付文書には「妊娠中の接種に関する安全性が確立していないので、原則として接種しない」となっているようですが、現在ではデータも蓄積され副作用に関する報告もありません。
医療は進歩していくので常に情報収集するといいですね。
妊婦さんにワクチンを接種することにより、生まれてきた赤ちゃんにも予防効果が期待できる、という報告もあります。
ワクチン接種後、効果出現には約2~3週間かかり、その後約3~4ヶ月効果が持続します。
そのため接種時期は10~11月からで、冬のインフルエンザのシーズンで2回の接種が望ましいといわれています。
普段からとれるインフルエンザの予防策
ワクチンでは必ずしもインフルエンザを予防できるわけではないのが悲しいところです。
ワクチンを摂取することでインフルエンザにかかってしまっても比較的症状が軽くなるといわれていますが、
日頃からインフルエンザに感染しないように予防することが何より大切ですよね。
インフルエンザ予防で気を付けたい5つのこと
①人込みに出ない
②正しい手洗い・うがい
③マスクを着用
④適度な湿度
⑤鼻呼吸を意識する
昨今の新型コロナウイルス感染拡大予防のために、マスクを装着する姿が当たり前の光景となっています。
マスクは人にウイルスを移さないために重要ですが、保湿効果もあるので感染予防としても大切です。
また、室内の湿度も50~60%程度を意識すると良いとされています。
ウイルスの感染力を抑えるために湿度を保ちインフルエンザのウィルスに感染しないよう気をつけたいですね。
参考:国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター:インフルエンザワクチン・薬情報
参考:妊娠・授乳とくすり
参考:日本産科婦人科学会/日本産婦科医会,産科婦人科 診療ガイドライン~産科編2020
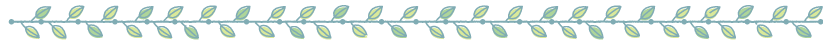
まとめ
今回はこれからの季節に気になる妊婦さんとインフルエンザについて調べてみました。
手洗い・うがい・保湿は2020年新型コロナウィルスの脅威にさらされた私たちにとって日常となり、例年よりも今年はインフルエンザが広がりにくいといわれています。
しかし、まったく感染者がいないわけではありません。
マタニティ期間を快適に健やかに過ごすためにも是非!予防に力を入れつつもしも感染したり、近親者に感染者が出た場合には最善の選択ができるといいですね。